| |
| 連載:高齢者の栄養管理とPEG |
| 第二回 PEG合併症総論と前期合併症 |
| ふきあげ内科胃腸科クリニック 蟹江治郎 |
|
| 臨床老年看護 2004; 11(2): 46-52. |
|
|
1.はじめに |
| 内視鏡的胃瘻造設術(Percutaneous Endoscopic
Gastrostomy、以下PEG)は,低侵襲で造設が可能で管理が容易なため,従来広く行われていた経鼻胃管に置き換わり,近年盛んに行われるようになった.しかし,PEGには経鼻胃管にはない外科的侵襲に伴う合併症や,管理のための特殊な知識が必要である.
本稿においては,PEGの管理を行う上で知っておかなければならない術後合併症の総論と,瘻孔が完成する前に発生する前期合併症の代表的な部分について,その原因と対処について論述したい. |
2.合併症の分類 |
| PEGは内視鏡を利用してチューブを挿入し,約3週間程度で瘻孔が完成する(図1).そのため一言PEG術後合併症といっても,瘻孔が完成する前と後ではチューブ挿入部の状態は全く異なり,合併症もその時期により異なった様相を呈している.よってPEGの合併症も瘻孔が完成する前と後で分けて理解する必要がある.本書においては瘻孔完成前の合併症については「前期合併症」と,瘻孔完成後の合併症は「後期合併症」として論述した.また前期合併症は非常に多岐にわたるため,感染性合併症と非感染性合併症に分類した. |
図1 胃瘻造設直後の胃瘻と瘻孔完成後の胃瘻
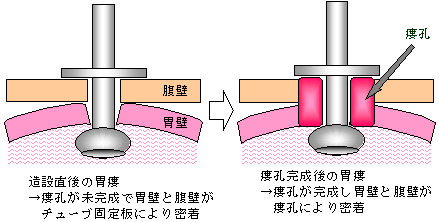 |
表1 PEG合併症の種類
| 前期合併症 (瘻孔完成前合併症) |
後期合併症
(瘻孔完成後合併症) |
| 感染に関連 |
感染に関連しない |
1)創部感染症
2)嚥下性呼吸器感染症(肺炎等)
3)汎発性腹膜炎
4)限局性腹膜炎
5)壊死性筋膜炎
6)敗血症 |
1)創部出血
2)再挿入不能
3)事故抜去
4)バルーン破裂
5)皮下気腫
6)チューブ閉塞
7)胃潰瘍 |
1)嘔吐回数増加
2)再挿入不能
3)チューブ誤挿入
4)事故抜去
5)胃潰瘍
6)栄養剤リーク(栄養剤漏れ)
7)バンパー埋没症候群
8)チューブ閉塞
9)挿入部不良肉芽形成
10)カンジダ性皮膚炎
11)体外固定板接触による皮膚障害
12)胃内固定板による胃腸通過障害
13)胃-結腸瘻 |
|
3.術後合併症の頻度 |
| 合併症の頻度について,著者が日本消化器内視鏡学会誌に報告した結果を表2に示す.651名の検討において合併症の頻度は30.0%で,感染性合併症は23.7%,非感染性合併症は6.3%との結果を得た.うち最も頻度の高かったものは創部感染症であった.重症化し,しばしば致命的となりうる合併症としては術後肺炎と汎発性腹膜炎を経験した.肺炎を含め術後呼吸器感染症は頻度的にも多く,もっとも憂慮すべき合併症といえるだろう.また早急な対処を要するものとして,瘻孔完成前の事故抜去も経験した. |
表2 術後前期合併症の頻度(n=651)
| 感染性合併症 |
|
非感染性合併症 |
| 創部感染 |
72例 |
|
事故抜去 |
7例 |
| 嚥下性呼吸器感染症 |
39例 |
|
チューブ閉塞 |
7例 |
| 短期発熱 |
31例 |
|
嘔 吐 |
6例 |
| 汎発性腹膜炎 |
4例 |
|
胃壁損傷 |
5例 |
| 限局性腹膜炎 |
4例 |
|
バルーンバースト |
5例 |
| 敗血症 |
3例 |
|
再挿入不能 |
5例 |
| 壊死性筋膜炎 |
1例 |
|
創部出血 |
3例 |
| |
|
|
皮下気腫 |
2例 |
| |
|
|
肝誤穿刺,腹壁損傷,
噴門部裂傷,胃潰瘍 |
各1例 |
| 計 154例(23.7%) |
|
計 41例(6.3%) |
|
4.術後前期合併症の原因と対処 |
1.創部感染症
原因:外科的手技に伴う合併症であるが,PEGの方法として広く行われているPull/Push法で高頻度に認める(表3).PEGの手技には,内視鏡を利用して口腔よりチューブを挿入する「Pull/Push法」と,内視鏡監視下に経皮的にチューブを挿入する「Introducer法」がある(図2).Pull/Push法においては,口腔を経由してチューブを挿入するため口腔内細菌を創部に移行することになり,創部感染の発生が増加するものと考えられる.
対処:創部消毒の回数を増やし抗生剤の投与も併用する.皮下膿瘍を形成する場合は,切開排膿が必要となる場合がある.胃内固定板と体外固定板の間隔が狭く,固定板圧迫に伴う創部虚血が生じているときは,創部感染の発生および悪化の因子となるので注意が必要である.
予防:Pull/Push法で造設を行う際は,術直前に口腔内をイソジンガーグルなどで充分清拭し,口腔内細菌の創部への移行を最小限にすることにより,創部感染の頻度を軽減する.術後は慎重に創部を観察し,体外固定板による圧迫が強くないかをチェックする. |
表3 創部感染症における造設手技間の発生頻度差
|
|
Pull/Push法 |
Introducer法 |
|
|
| 創部感染あり |
69例(13.0%) |
3例(2.5%) |
72例 |
| 創部感染なし |
463例(87.0%) |
116例(97.5%) |
579例 |
|
|
532例(100%) |
119例(100%) |
651例 |
|
χ2test:p=0.001 |
図2 胃瘻造設法の種類
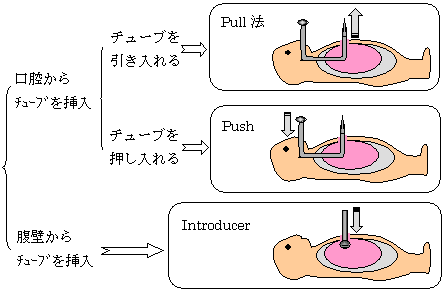 |
2.嚥下性呼吸器感染症
原因:胃内視鏡は本来,誤嚥を防止する目的で側臥位での挿入を行い,唾液は嚥下しないよう体外に流出するよう促している.しかしPEGについては,仰臥位で内視鏡操作を行うため,唾液の自然流出が行えない.またPEGの対象者は嚥下障害を有する症例が多く,結果的に手術操作により誤嚥を惹起する事になる.
対処:一般的な肺炎治療に準ずる.状態の悪化により嘔吐などを生じるときは,PEGを開放状態にして胃を減圧し,胃食道逆流による更なる誤嚥を防止する.
予防:術前より抗生剤の予防投与を行うことが効果的である.また術中の誤嚥を防止する意味で,内視鏡挿入中は頻回の口腔吸引を行う.日頃より口腔ケアを怠らないことも重要である. |
3.汎発性腹膜炎
原因:外科的手技に伴って発生する合併症である.筆者の経験では,胃腹壁間離解に伴い発生する例を多く認めた(表4).瘻孔完成前のPEGは,チューブの体外固定板と胃内固定板の牽引により胃壁と腹壁が密着している.この密着を持続することで瘻孔は完成し胃壁と腹壁とが癒着するが,瘻孔が完成する前にチューブ事故抜去などが発生すると,胃壁は胃内固定板による腹壁への挙上がなくなり,胃壁と腹壁が離解(=胃腹壁間離解)することになる.瘻孔完成前の胃腹壁間離解は,胃穿孔と同一の状態であり腹膜炎の原因となる.
症状:PEGの対象となる症例は,痴呆や意識障害により自覚症状を充分訴えられない場合が多い.その様な症例では,非定型的な経過をたどり,発熱や麻痺性イレウスによる嘔吐などで突然発症することがある.健常者と比較しても,重症度の割に症状が軽いこともあり注意が必要である.
対処:原則的には開腹洗浄および腹腔ドレナージ術が必要になり,迅速な対応が必要となる.
予防:発生誘因として不意に発生する胃腹壁間離解があり,筆者はこの予防の目的で「経皮胃壁固定術」をPEG施行者全員に行うことを推奨している.この経皮胃壁固定術とは,PEGに先立ってチューブ挿入部の胃壁と腹壁を縫合する方法で,瘻孔完成前にチューブ抜去が生じても,胃壁と腹壁の密着が保持される事になる(図3). |
表4 急性期汎発性腹膜炎の発生誘因
|
| 経皮胃壁固定を行わない症例での事故抜去による胃腹壁間離解 |
2例 |
|
| 経皮胃壁固定が不意に外れた事による胃腹壁間離解 |
1例 |
|
| 発生誘因なし |
1例 |
|
|
| 合計 4例 |
|
|
蟹江治郎:内視鏡的胃瘻造設術における術後合併症の検討 ― 胃瘻造設10年の施行症例より ―,
日本消化器内視鏡学会雑誌 2003; 45(8): 1267-72 |
図3 経皮胃壁固定法
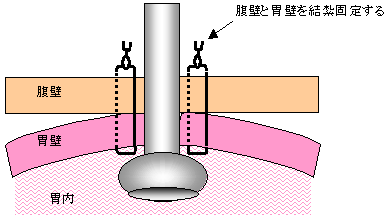
蟹江治郎:胃瘻PEGハンドブック,医学書院,東京. |
4.瘻孔完成前事故抜去
原因:自己または他者によるチューブ牽引や,バルーン破裂などの胃内固定板の脱落により発生する.このように不意にチューブが抜去してしまう状態を「事故抜去」を呼ぶ.
症状:瘻孔完成前に事故抜去が生じると,経皮胃壁固定術を施していない場合は胃腹壁間離解が生じ,胃内容物が流出すると汎発性腹膜炎が発生する.
治療:瘻孔が完成していない場合は,胃穿孔と同様の状態になる.しかし理学所見のみでは術後早期の瘻孔完成の有無について判別が困難である.そのため事故抜去が生じた際は,経鼻胃管による胃内減圧と抗生剤の投与で厳重に観察し,腹膜炎の徴候が生じるようなら開腹洗浄ドレナージを考慮する.
予防:不穏状態のためチューブ牽引の可能性がある場合は,腹帯で患部を覆い手が届かないよう配慮が必要である.不穏が強く明らかにチューブ牽引のおそれがある場合は,経皮抜去が不可能なPEGキットや手の届きにくいボタン型のPEGキットを選択することが望ましい.またバルーン型で造設した場合は,バルーン破裂の危険を認知した上で定期的な破裂の有無の確認を行い,術後早期はテープによる固定を併用すると良い. |
図4 瘻孔完成前事故抜去
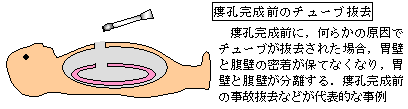 |
5.チューブ閉塞
原因:14Fr以下の細径チューブで造設を行ったときなど,チューブの内腔が狭く薬剤が詰まるなどの問題が生じることがある.特にバルーンチューブは経鼻胃管に比較してチューブの壁厚が厚く,意外に内腔が細いことが多く注意を要する.
症状:薬剤注入時に発生することが多い.
対処:チューブの交換は瘻孔が完成する前である術後3ヶ月以内は禁忌のため,チューブの開存を試みる.方法としてはチューブ内腔を水で満たした後に,細径プジーなどを通して閉塞部位の開通を行う.最近ではPEG専用の洗浄ブラシ(PDNブラシ:PEGドクターズネットワーク販売,03-5733-4361)も販売している.何れの方法でも開存が得られない場合は,瘻孔が完成するまで,一時的に経鼻胃管栄養で凌ぐ事になる.
予防:特に14Fr以下の細径チューブでPEGを行ったときは,可能な限りドライシロップなど溶解する薬剤を選択する.やむを得ず顆粒の注入を行うときは,多めの水で慎重に注入を行う. |
6.創部出血
原因:外科的処置に伴う合併症であるが,筆者の経験では予期せぬ出血傾向を持つ症例に対してPEGを行ったときに多発する傾向にあった(表5).
対処:止血剤の投与に加え,出血傾向の確認が必要である.
予防:手術に先立って,血小板凝集抑制薬などの出血傾向を起こす薬剤は,可能な限り休薬する.また他の外科手術同様,出血傾向のチェックを行うことが望ましい. |
表5 筆者治験例における術後出血の経験
|
慢性嚥下性呼吸器感染症により,長期にわたり抗生剤の投与が行われており,
腸内細菌の変動に伴うビタミンK欠乏により出血傾向を生じた. |
2名 |
| 術前より血小板凝集抑制薬の与薬が行われており出血傾向を生じた. |
1名 |
|
|
5 おわりに |
| PEGを行うということは,単に内視鏡で胃にチューブを挿入するだけだけではない.PEGチューブを挿入した後も,トラブルが起こらないよう監視が必要である.PEGで起こりうるトラブルには管理を怠ることにより発生する医原性の要素の強いものや,致命的になる重要なものもある.トラブルを未然に防ぐためには,先ずPEG術後にどの様なことが発生し得るかを,熟知しておくことが重要である.本稿においては,PEGの合併症には何があるか,そしてその早期合併症として代表的なものについて記述を行った.次号では瘻孔完成後合併症について細説する予定である.本稿と合わせて理解を頂くことをお勧めする. |
引用・参考文献 |
|
|